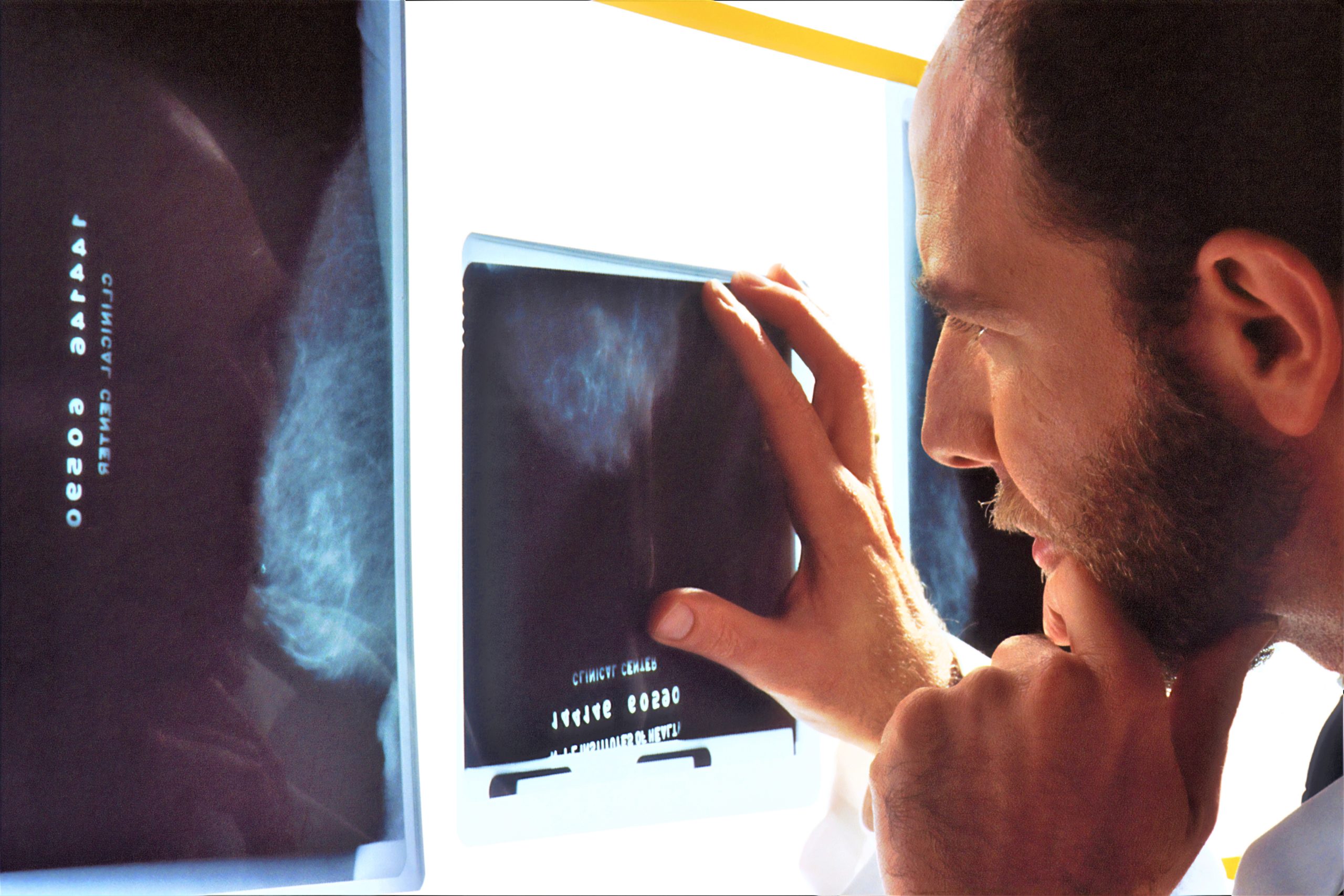※最終章に関しては11)から順にお読みください
最終章の目次
11)最終章Ⅰ-動機ー
12)最終章Ⅱ-痛みとプラセボ効果-
13)最終章Ⅲ-心と痛みの関係-
14)最終章Ⅳ-生きる-
閑話休題。
ぼくは理学療法科の主任を数年つとめた後、別の整形外科に副院長として赴任した。そこにおいては、独自の観点から患者さんを見つめ直す作業を試みた。
腰痛や肩こりに悩む患者さんのなかには、あらゆる治療に反応しない人、あるいは反応しても再発を繰り返す人がいる。ぼくはかねてからそういった人々の社会背景や気質に注目しており、心の面からアプローチする必要性を感じていた。
精神医学や心理学の勉強と共に、臨床では痛みに悩む人々の心の扉をノックする日々が続いた。こちらが問いかける以前に、内情を積極的に吐露してくれる人もいたし、精神的な話を避けたがる人もいた。
しかしそういった作業は想像以上にしんどいものだった。当然時間的な制約があったし、副院長として診療全体のバランスも考慮しなければならなかった。
毎週のように院内で勉強会を開き、スタッフらの考えも参考にしながら、ぼくの主意に理解を求めた。
そうして痛みに悩む人々の心の背景が徐々に浮き彫りになってゆくなか、ぼくは六十代前半の或る女性の治療を担当した。
数年来の頑固な腰痛に悩まされているKさんは、大学病院で検査してもこれといった異常が見つからず、ありとあらゆる治療を試みてきたがいっこうに改善しなかった。
そんな折彼女は、ぼくが個人的にやっている特殊な手技療法の評判を聞いて来院した。
ぼくの治療にもやはり反応は薄かったのだが、三回目の治療時から少しずつ家庭のことを話してくれるようになった。ぼくは時間の許す限り、彼女の話に耳を傾けた。
彼女の話の詳細はここでは話せない。ただ一つ言えるのは、今の社会においては彼女の境遇が決して特別ではないということ。
しかし、彼女の苦悩はいまにも押し潰されそうな逼塞感に呻吟する現代人の、心の悲鳴を象徴したものだった。
何かが彼女の琴線に触れたのだろう。ぼくのところに一年近く通ってくれたが、症状は治療直後だけ改善し、数日後に再発する状態が続いていた。
そんなKさんの症状がある日を境に劇的に快方に向かった。ぼくの治療が効を奏したのではない。毎回同じ治療をしていたのだから、それは間違いない。
考えられる理由は一つしかなかった。彼女の心に打撃を与え続けていた或る事情が奇跡的に好転したのだ。出口の見えない袋小路からようやく抜け出すことができたのである。
それ以来彼女は元気を取り戻し、あれほど苦しんでいた腰痛から解放された。
もっともKさん自身は、ぼくの治療によって治ったと思い込んでいたので、ちょっと複雑な気分ではあった…。
実はこのようなことは決して珍しいことではなかった。カウンセリングなどと言うと、本職の方に叱られてしまいそうなほどに稚拙なものだったと思う。
しかし、そんなぼくとの対話を通じてさえも、明らかに症状が落ち着く患者さんが少なくなかった。
心の扉に鍵がかかったままの人には無力だったが、それとは対蹠的に治療後の何気ないコミュニケーションのなかで、患者さん自身が自力で内心の扉を開き、無意識に封印していた心の傷と向き合うことによってはじめて痛みから解放された人もいた。
ところで、このような心と痛みの不思議な関係について、最近ではぼく以外にも指摘している臨床家は多い。
ただ、そのようなケースは少数なのか、あるいは多数なのかという議論があった。ぼくが一番知りたかったのはまさにそこのところだった。
ここから先は、その後の臨床経験値を総動員して得られた「一つの可能性」(ちょっと控え目な表現)、あるいは「答え」(ずいぶん強気…)である。
前述したとおり同じ「痛み」でも、皮膚痛覚や急性痛については解明されつつあるが、深部感覚における慢性痛に関しては科学的に判明していないことが多い。それを念頭に置いて聞いて欲しい。
「けがをした覚えがないのに痛みを感じたことは?」と尋ねると、「そんなことは一度も経験したことがない」という人がいる一方で、「ある」と答える人もいる。ではどんなときに感じるのか?
久しぶりに運動したり、引越しを手伝ったり、部屋のリフォームをしたり、長時間の同一姿勢を強いられたり、激しい緊張にさらされたり…。
こうした体験のあとに感じられる痛みは放っておいても自然に消えることが多い。我々には本来そういう自己修復能力が備わっている。現代人は身内に潜む「野生の力」をもっと信頼すべきた。
ところが、このレベルの人たちが「患者さん」になった場合、つまり自然に治るはずの人が病院に行ってしまった場合、いかなる治療にも反応するので、治療者は自分が治していると思い込む。
治療者に間違った矜持を与える「患者さん」である。
その程度の患者さんにとってむしろ怖いのは、実際はたいした病気でないのに、レントゲンに描出された骨の変化(たとえば骨の老化は痛みの原因にはならない。これは科学的に立証されている)を医師から強調され、病気の程度を必要以上に悪く認識してしまうことである。
そう思い込むことによって、本当に重い病気になってしまうことが実際にあるのだ。
これは言わば「逆プラセボ効果」になっている。専門用語では「ノセボ」という。負の暗示効果と表現することもできる。
逆プラセボに陥ることがなく、尚且つ生活背景に強い心理的抑圧がなければ、治療の有無に関わらず痛みは自然に消える。
ところが、そこに心理的なストレスの増悪が重なったり、あるいは長期にわたって持続したりすると、痛みは単なる生理現象を超えて心の動きと密接に連動するようになる。
抑圧された怒り、不安感、プレッシャー、気分の落ち込みなどによって痛みが増強し、その痛みの存在にまた落ち込む。するとさらに痛みが強くなる。究極の悪循環…。このレベルになると、ちょっとやそっとでは治らない。
ある種の強い「思い込み」が良い方向に働いた場合のみ、自然治癒力が働く。そのきっかけとなり得るのがまさしく「プラセボ効果」である。
代替療法の中にはこれをうまく利用しているケースが多い。したがって慢性痛に対する医療にこそ「比較対照試験」が必須と言えるのだ。
治療技術云々ではなく、プラセボ効果を上手に引き出してあげる「先生」こそが名医とよばれる、そういう世界…。
さて、以上の背景を踏まえて「筋骨格系の慢性痛の存在理由とは何なのか」という問いに答えたい。
『心に痛覚はない。どんなに心が傷ついてボロボロになっても、心は痛みを感じない。人間は「先天性こころ無痛症」と言える。
先天性無痛症の子供が肉体の痛みを感じないのと同様に、ほとんどの人類も心の痛みを知覚することができない。
そこで、脳は心の危機を知らせるシステムの一環として、痛みを利用し始めた。それが慢性痛の起源である』
ぼくが主導した整形外科でのプロジェクト(全症例の心理面を分析)によって、毎日のように物療室に通ってくる慢性痛の患者さん…、その多くが程度の差はあれ何かしらの心理的背景を抱えていたのである。
そしてその因果関係としての順番は「痛いからメンタルが…」ではなく、「メンタルに関わる事象が先行して、その後に痛みが…」であることも確認した上での結論である。
したがって心と痛みが相関しているケースは少数ではなく、むしろ圧倒的多数だと、ぼくは考えている。
医学の歴史上はじめて慢性痛という言葉が生まれた1960年代は、東京オリンピックを経て日本が高度経済成長時代にまっしぐらに突き進んだ時代である。
その時期に一致して、長期にわたって続く腰痛や肩こりの存在を医療者が認識し始めたことは決して偶然ではない。
とくに近代史上稀に見るスピードで経済を復興させた日本では、その社会構造の複雑化に伴ってストレッサーが多様化し、慢性痛も爆発的に増えていった。
医学は日進月歩の世界だ。近い将来にまったく次元の違う画期的な答えが出るやも知れぬ。
しかし、ぼくの出した結論が中心からそんなに離れているとは思えない。
ぼくのような無名の一市民が主張したところで、あまり説得力がないかも知れないが、最後にこれだけは是非とも言っておきたい。
レントゲンやMRIといった画像診断に頼り切っている西洋医学は、そのような形而下的な哲学から脱却しない限り、心と密接に関係している「人間の痛み」の本質にはとうてい近づくことはできない。
肩に力が入り過ぎたようだ。首筋が張ってきたので、またぼくの内面の話に戻りたい。
◆
と言っても、自身の内実を話すのもけっこうしんどい作業だったことを忘れていた。しかし続けよう。ここまで来たら後戻りはできない…。
ぼくが副院長としてつとめたクリニックでは、その経営者からある使命を授かっていた。経営の立て直しである。
幸い素晴らしいスタッフに恵まれ、ぼくはその役割を果たすことができた。
しかし、患者さんに施す理想の医療と経営的な実情の上に成り立つ現実とでは、あまりにギャップがあり過ぎた。どうやってそのバランスをとれば良いのか、ぼくの精神は激しく揺れ続けた。
その答えは、突きつめれば日本の医療制度そのものにあるのだが、個人レベルで解決できる次元の話ではない。
同じ頃、接骨師の学会で或る論文を発表したが、会場の無反応ぶりに心の底から落胆した。整形外科よりもむしろ接骨院でこそ、重要なテーマを孕んでいる論文だったのだが…。
そして日々の臨床においては、痛みに対する一つの答えがぼくのなかに出てしまった。
前述の「痛み」の答えだ。実際にそれが的を射ているかどうかは別として、少なくともぼく自身はその結論を信じている。
しかしそれは同時に、接骨師としての自分の存在意義を失いかねない答えになっていた。
◆
妹尾河童氏の「少年H」という小説にも描かれている通り、戦前から戦後までは、市井の人々は骨折などのけがをすればたいてい接骨院(ほねつぎ)へ行った。
当時は街角に整形外科はなかった。外傷は外科の医師が診ていたが、不慣れな外科に行くよりも接骨院に行った方が安心だった。皆そう考えていた。そういう時代だった。
翻って現代、大きな外傷はたいてい救急車で医療センターに運ばれる。入院施設のない整形外科(個人の開業医)に重篤な患者さんが来るケースは稀である。
たとえば鎖骨骨折の場合、家族がある程度面倒をみる必要があるが、核家族化が進み、共働きが増えている今日では患者さん本人ではなく、家族が入院を希望するようになった。
こうした時代背景の下、骨折の患者さんが接骨院に通うケースは年々減ってきている。
昨今の画像検査技術の発展(三次元CT、MRI等々)は目覚ましいものがあり、画像情報のない外傷管理は医学的にNGと言わざるを得ない。
法律上レントゲン検査すら許されない接骨院、画像診断権を持たない接骨師が本来のアイデンティティ(外傷に対する保存療法のスペシャリスト)を維持することは甚だ困難な時代になったと言える。
こうした背景を踏まえ、先述したとおり運動器プライマリケアの理想像は「手術の専門家(整形外科医)と保存療法の専門家(接骨師)がタッグを組む医療体制」だという自論に辿り着くのである。

上の画像は三上式プライトン固定(著者が開発した拘縮予防のための機能性固定装具)。一般に整形外科が行うギプス固定は巻いたら数週間そのままの状態が続く。これは皮膚の問題を併発しやすく、関節拘縮(関節が固まる)リスクも高まるが、三上式プライトン固定は状況に合わせて脱着が可能で、皮膚のケアが容易であり、かつ関節拘縮を起こしにくいという最大の利点がある。
こうした技術は整形外科医にはない。接骨師だけが持ち得る特殊技能である。
しかし先述したとおり、日本の医療制度はあらゆる権限を医師が独占する完全ピラミッド構造であり、整形外科医と接骨師が対等な関係でチーム医療を行うことなどあり得ない…。
ぼくはたまたま理解のあるオーナーの下、整形外科の副院長というポストに就いたが、これは異例中の異例…。
今、接骨師の多くは痛みの患者さんを相手にして糊口をしのいでいる。ぼくもいずれは父の跡を継いで自宅の接骨院に戻ることになるだろう。そのとき、果たしてどんなモチベーションでいられるだろうか。
整形外科でのキャリアは、結果的に資格の壁と痛みの真実をぼくに突きつけることになった。
痛みに苦しんでいる人を真に救うには、心のアプローチが必須であり、既にその本職の人たち(心療内科医やカウンセラーなど)が実績を上げている。接骨師という資格の枠組みでできることは本当に限られている…。
これ以上何を勉強すればいいのだろう。どんなテーマに向かって進めばいいのだろう。
副院長として充実した日々を送る一方、ぼくは自分の中の何かが崩れ始めているのを意識の奥底で感じていた。
→最終章Ⅳ-生きる-に続く
「軽井沢/エッセイ」-目次(リンク表示)
1 ミレニアムの夜明け
2 音楽療法
3 天明の大噴火
4 自然と五感と恋心
5 青天の霹靂
6 湯川の森-ヒグラシの調べ-
7 湯川の森-精霊のウィンク-
8 コスモス畑
9 稚児池
10 避暑地の猫
11 最終章Ⅰ-動機-
12 最終章Ⅱ-痛みとプラセボ効果-
13 最終章Ⅲ-心と痛みの関係-
14 最終章Ⅳ-生きる-
(C)2001三上敦士